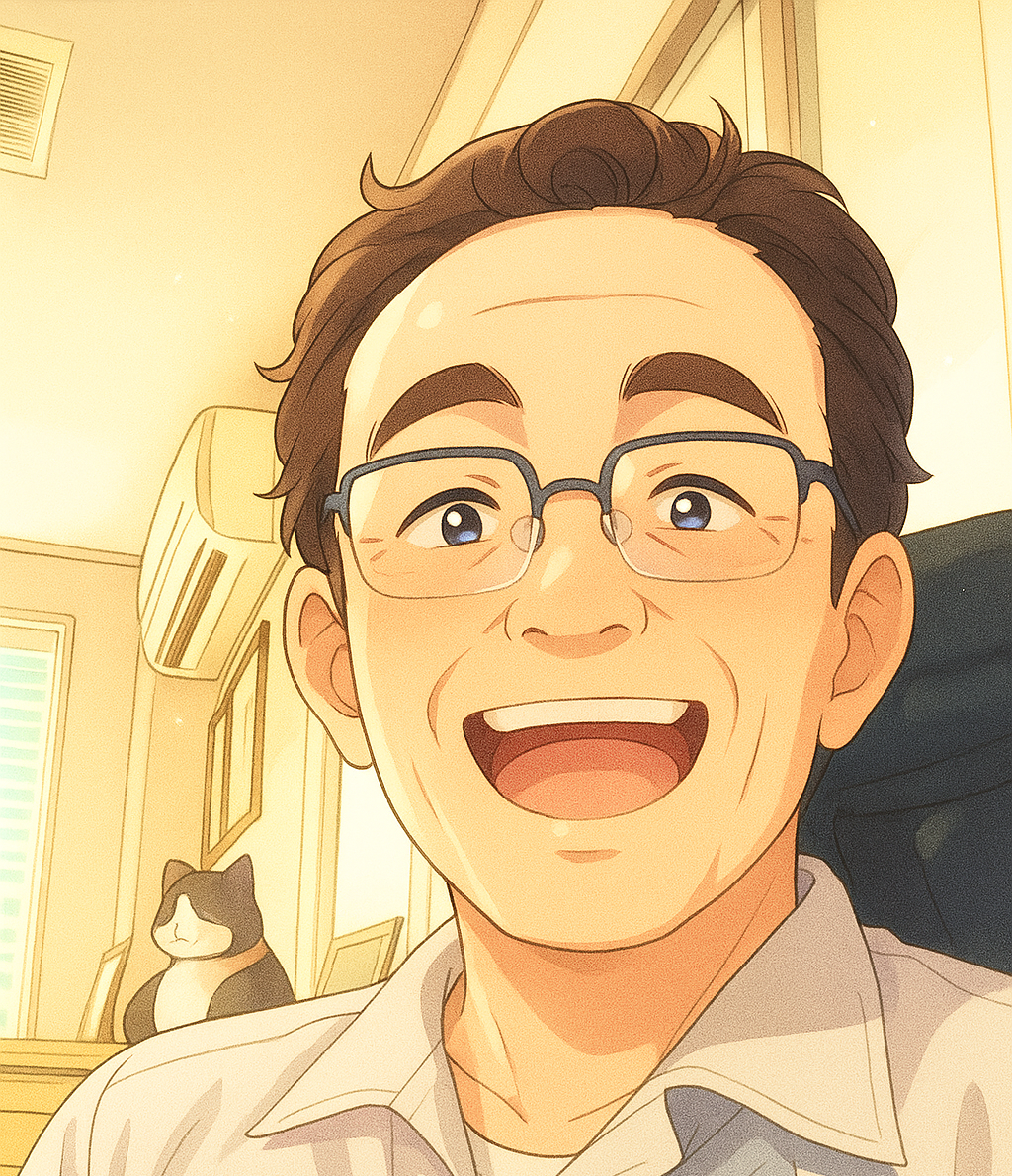― 失敗を糧に歩んできた61歳が見た「資産運用スクール」の本質 ―
はじめに
私は1964年生まれ、現在61歳。
アルミ加工を主力とする製造業の会社を経営しています。
社員・派遣スタッフを含めて約45名と日々現場を動かしつつ、趣味では韓国ドラマやソフトボール、ゴルフ、そして長年親しんできた麻雀で気分転換をしています。
経営の裏では、過去に副業案件へ多額を投じて借金を抱えたり
私生活で離婚を経験したこともありました。
それでも「次こそは成果につなげたい」と挑戦をやめずにきました。
そんな自分の視点で「ハナミラ」という投資スクールを検証していきます。
ハナミラとはどのようなサービスか

ハナミラは松下りせ氏が案内役を務める「資産運用スクール」です。
主に株式投資を中心に
資産形成やマネーリテラシーを学べるとされています。
コンセプトとして掲げられているのは「お金を増やすための技術」ではなく、
「理想の人生を手に入れるための資産形成」です。
つまり、単なる投資手法の伝授ではなく、心構えやライフスタイルの変化まで意識した“教育型プログラム”という立ち位置を取っています。
表現としては魅力的ですが、収益化の仕組みはやや抽象的です。
実態を深掘りすると見えてくる課題
公開されている情報を掘り下げてみると、次のような特徴が見えてきます。
- 松下氏本人の投資実績や専門資格は確認できない
- 成果の再現性を示す数値データや検証は不十分
- 動画やセミナーは「マインドセット」に偏り、具体的な銘柄分析や運用プロセスが薄い
この構成からすると、ハナミラは「投資スクール」というより
「投資マインドを高めるコミュニティ型コンテンツ」の色合いが濃いといえます。
無料プログラムから有料講座へ
無料で提供される「投資家デビュー3daysプログラム」は
投資の必要性や将来不安を強調する内容が中心です。
ここで興味を持った人を有料講座へと誘導する流れになっています。
マーケティング構造としては、いわゆる
「フロントエンド商品(無料)→バックエンド商品(高額有料)」
という典型的なビジネスモデル。
ユーザーの心理を「無料なら損はない」と動かし、その後に「さらに学ぶならこちら」と高額プランを提示するわけです。
有料講座のビジネス構造
実際の有料プログラムは、投資スクールとして数十万円規模の金額になると噂されています。
講座そのものが投資対象ではなく、あくまで「学び」への支払いです。
つまり、参加者が本当に利益を得られるかどうかは保証されていません。
運営サイドの収益は「教材費+コミュニティ参加費」によって成立しており、投資で利益を出す構造ではないのです。
この仕組みは、「投資で稼ぐ」よりも「教育を売る」ことが収益の中心になっている
典型例だといえるでしょう。
経営者として見たリスク

私は製造業の現場で長年「数字の裏付け」を重視してきました。
売上や利益を語るときには、必ず原価や工程が見える必要があります。
投資教育ビジネスにも同じことが言えます。
ハナミラには「人生設計」「マインド」といった言葉は並んでいますが、具体的に「どの銘柄をどう分析し、どのように利益につなげるのか」という数値的なロジックが不足しています。
これは経営的な視点から見ると、大きなリスク要因です。
口コミと評判の温度差
ネット上の口コミには「詐欺ではないが稼げない」「マインドばかりで実践性が薄い」
といった声が見られます。
一方で「仲間ができた」「意識が変わった」というポジティブな意見も存在します。
この温度差が示しているのは
参加者が何を求めるかによって満足度が大きく変わるということ。
具体的に収益を得たい人には物足りなく
モチベーション維持を求める人には価値を感じやすい構造だといえます。
まとめ

ハナミラは「資産形成を学ぶスクール」としては一定の価値があるかもしれません。
しかし、「誰でも投資で利益を出せる」といった直接的な実績の裏付けはなく
再現性の低さが最大の懸念点です。
ビジネスモデルとしては「教育型コンテンツ販売」が中心であり
投資そのものからの利益ではありません。
つまり、参加者にとっては「投資を学ぶ場所」であっても「投資で稼げる保証のある場所」ではないということです。
経営者として強調したいのは
夢やマインドではなく、数字に裏付けられたロジックを確認してから動くこと。
副業や投資に挑戦する人は、派手な宣伝よりも「再現性」と「透明性」を基準に選ぶべきです。